ネットのプライバシー権とは?自己情報コントロール権との違いを解説
近年プライバシー権の重要性が高まり、その権利内容が拡大されてきています。そこで今回は、プライバシーの侵害になる基準や…[続きを読む]
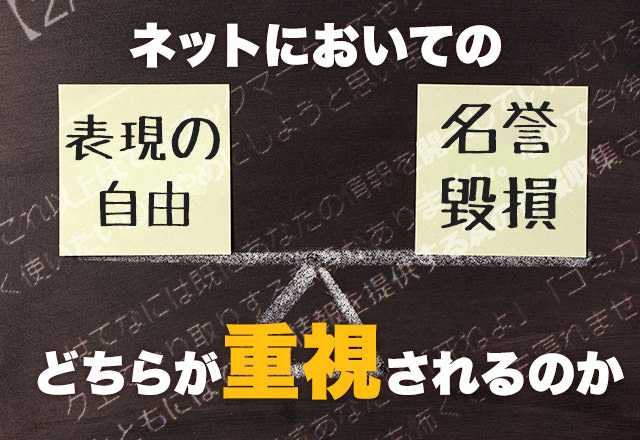
SNS上では、誹謗中傷的な表現が問題になることが多いです。特定の人や法人を誹謗中傷すると、名誉毀損や侮辱罪などが成立して、刑罰を科されるおそれがありますし、慰謝料支払いが必要になることもあります。
しかし、日本国憲法では「表現の自由」が保障されているはずです。ネット上の自由な表現が、どうして認められないことになるのでしょうか?
今回は、憲法が保障する表現の自由・言論の自由のこととインターネット・SNSでの名誉毀損との関係、有名な事例、問題点などについて、 わかりやすく解説します。
目次
インターネットを利用するとき、表現行為は避けて通ることができません。
ブログやコメント、ホームページによる宣伝やツイッター、各種のSNSなど、どのような文書を書くときにも、イラストや写真を投稿するときにも、人は「表現」をしています。
この権利は、憲法21条によって明確に保障されています。言論の自由も表現の自由の一内容として保障されます。
憲法21条には、以下の通り規定されています。
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
憲法は、国の最上位の法律であり、他のどの法律や制度によっても害されることはありません。
そうすると、憲法が表現の自由を認めている以上、表現の自由は誰にも侵害をされてはいけないものだということになります。
このように、表現の自由が重要視されているのは、表現の自由が民主主義の基礎となる根本的な権利だからです。
表現の自由には、2つの価値があります。
1つは、自分の精神を外部に表現することで自己実現をする価値です。
人は、自分の意思を表現したり、他者の表現を感得したりすることによって自分の考え方を深めて成長していくものです。
このような価値のことを、自己実現の価値と言います。
もう1つは、表現をすることによって「政治的な意思決定」に関わることができる価値です。
民主主義では、国民自身が政治に関わる必要がありますが、そのためには、国民のひとりひとりが自由に自分の意見を述べることができることが大前提となります。
このことを、自己統治の価値と言います。
表現の自由は、上記の通り、自己実現と自己統治の価値を持っており、民主主義の根本的な基礎となる重要な権利であるため、数ある人権のうちでも「優先的な価値」を持っている(優越的地位と言います)と考えられています。
ネット上でいろいろな表現をすることも、すべてこの「表現の自由」によって保障されているのです。
実際に、ネット上で誰かを誹謗中傷すると、相手に対する名誉毀損などが成立することが知られていますが、これは「表現の自由」への不当な制限ではないのかと疑問を持つ人もいるでしょう。
確かに表現の自由は重要な権利ではありますが、無制限の権利ではありません。
憲法上保障される人権は、すべての人に認められるものではありますが、相互にぶつかり合うことを避けることは不可能です。
たとえば、人間には人身の自由があるのでどこに行っても自由なはずですが、他人の敷地に勝手に進入すると、他人の財産権やプライバシー権を侵害することになってしまいます。
そこで、人権相互がぶつかり合う場面にそなえて、それを調整する工夫が必要になります。
まず問題になりやすいのは、プライバシー権との対立です。
プライバシー権とは、私生活に関する情報をみだりに開示されない権利のことです。
憲法では「プライバシー権」を明文上保障はしていませんが、これは、人格権の基本となるものなので、憲法13条によって保障されると考えられています。
表現活動によって、他人の知られたくない私生活上の情報を明らかにすると「プライバシー権侵害行為」と評価されます。
現代では、プライバシー権によって保障される範囲はかなり広く理解されています。
家族関係や年齢、住所、氏名、電話番号やメールアドレスなどの個人情報についても、インターネット 上に勝手に記載するとプライバシー権侵害となってしまうので、注意が必要です。
表現の自由との関連で、プライバシー権と並んで問題になりやすいのが、名誉権です。
また、表現行為によって、人の社会的評価を低下させる内容を明らかにすることを「名誉毀損」と言います。
しかし、表現の自由が保障されているからといって、他者の名誉権を侵害してもよい、ということにはなりません。
インターネット上で他者について書き込むときには、名誉毀損にならないよう、十分配慮が必要です。自分では意識していなくても、名誉毀損と受け止められることはよくあります。

それでは、名誉権と表現の自由は、どちらが優先されるのでしょうか?
表現の自由によっても名誉権を侵害することが許されないなら、名誉権の方が優先されるようにも思えます。
しかし、これについて、「どちらが優先される」ということはありません。
両者は、両方とも人格権の中心をなす重要な権利なので、どちらかを一方的に保護することはできないのです。
両者のバランスは、法律によって調整されているので、表現活動をするときには、その調整の方法や内容を理解しておく必要があります。
それでは、具体的に名誉権と表現の自由の調整はどのようにはかられているのか、法律の規定を確認しましょう。
名誉権と表現の自由の調整をする規定としては、名誉毀損罪(刑法230条)が代表的です。
他人の名誉権を侵害する表現行為をすると、名誉毀損罪という犯罪が成立するためです。そこで、まずは、名誉毀損罪の基本的な成立要件を見てみましょう。
名誉毀損罪は、以下の場合に成立します。
以上のように、事実を示し、人に広まっていく可能性のある方法で、人の社会的評価を低下させる表現行為をすると「名誉毀損罪」になります。
つまり上記のような程度を超えると、表現の自由よりも名誉権が優先されるということです。
ちなみに名誉毀損罪が成立すると、3年以下の懲役または禁固、50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
名誉毀損罪が成立する場合は、基本的に前項で説明したとおりですが、以下の要件を満たす場合には、違法性が阻却されると考えられています。
「違法性の阻却」とは、外見上犯罪に該当するように見えても、違法性が認められなくなって犯罪が成立しなくなるということです。
名誉毀損罪で違法性が阻却されるためには、以下の3つの要件を満たすことが必要です。
この3要件は、刑法230条の2に規定されています。
公共の利害にかかわる、というのは、たとえば「公務員の収賄や議院、政治家などの過去の逮捕歴・前科に関する情報」などです。
こうした情報は、国民が適切に政治的な意思決定をするためにも必要です。事実が人の犯罪行為(公訴提起前)に関する場合にも、公共の利害に関する事実とみなされます(刑法230の2の第2項)。
そこで、人の前科や起訴前の犯罪事実(嫌疑がかかっている事実)について表現を行った場合、下記の2つの要件を満たせば、名誉毀損罪は成立しません。
名誉毀損罪の違法性が阻却されるためには、私利私欲による表現行為ではなく、「国や国民全体、社会全体の利益をはかる」というような、公益目的を持って表現行為を行ったことが必要です。
名誉毀損罪の違法性が阻却されるためには、表現した内容が真実であることの立証が必要です。
名誉毀損罪は表現した内容が事実であってもなくても成立しますが、違法性が阻却される可能性があるのは、「真実を表現した場合」に限られます。
名誉毀損罪の違法性阻却事由が適用されるためには、基本的には真実性の立証が必要ですが、これについては判例によって要件が緩和されています。
後述致しますが、夕刊和歌山時事事件という事件において、実際に真実性の立証ができなくても、表現行為を行った時点において、その内容が事実であることを信じており、信じるに足りる十分な根拠や確実な資料があったときには、故意が認められず、名誉毀損罪が成立しなくなる、と判断されています。
表現の自由と名誉権について、摘示される事実の内容によっては、さらに細かく調整がはかられています。
それは、摘示した事実が「公務員や公務員の候補者に関する事実」である場合です。
この場合には、真実性の証明があれば、名誉毀損罪が成立しなくなります。
つまり、公共の利害に関する事実であることの証明と、公益目的の証明が不要になります。
公務員や公職の候補者に関する事実であれば、公共の利害に関する事実であることと公益目的があることは当然の前提と考えられるのです。

次に、表現の自由に関して、どのような判例があるのかを見てみましょう。
この事件は、「宴のあと」という小説によって私生活を公開された人が、小説家を相手取って起こした訴訟です。ここで裁判所は、プライバシー権を人権として認めました。そして、プライバシー権侵害として認められるためには、
の3つの要件が必要であると判断しました。
そして、表現の自由はプライバシー権に優越しないと述べて、表現行為によるプライバシー権侵害の違法性を認めました。
この事件では、「石に泳ぐ魚」という小説の登場人物のモデルにされた人が、プライバシー権にもとづいて出版社に差し止め請求をしました。
裁判所は下記のように、侵害行為の差止めを肯認すべきと判断しました。
その上で、プライバシー権侵害を認めて、差し止め請求を認容する判断をしました。
この事件は、名誉毀損罪の違法性阻却事由である、「真実性の立証」について問題になったものです。
具体的な事案の内容としては、夕刊和歌山時事という新聞において、他社の取材方法(市役所職員に対するもの)を「恐喝まがい」と書いたことについて、名誉毀損罪の成立が問題になりました。
先にも説明しましたが、名誉毀損罪では、以下のような違法性阻却事由があります(刑法230条の2)。
ただ、実際に真実性を立証するのはかなり難しいです。
そこで、この裁判では、真実であることの証明がない場合であっても、下記のような場合は犯罪の故意はなく、名誉毀損罪が成立しないと判断しました。
この判断は、名誉毀損罪の違法性阻却要件を緩和したものと理解されており、その後の同様の裁判における有名なモデルケースとなっています。
今回は、インターネット上の誹謗中傷などでよく問題になる「表現の自由」とその制限、有名な事例などについてわかりやすく解説しました。
インターネット上で誹謗中傷行為を行うと、表現の自由が認められるとは言ってもさまざまな違法行為として評価されてしまうので、注意が必要です。
インターネット上の表現行為の違法性は、最終的には司法の場で判断されるため、何かわからないことがあったり悩み、疑問、迷いがあったりしたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。