送信防止措置依頼書の書き方【入門編】
プロバイダ責任制限法では、被害者に「送信防止措置請求権」「発信者情報開示請求権」を認めています。誹謗中傷の該当記事を…[続きを読む]
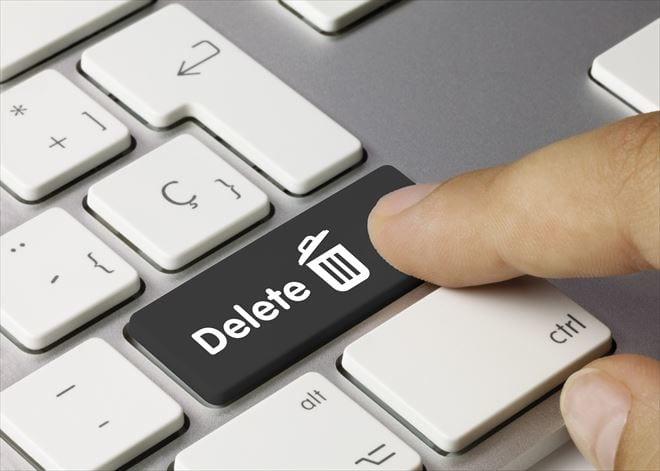
近年では、誹謗中傷・名誉毀損・プライバシー侵害など、様々なネットトラブルが発生しています。
インターネット上でこのような被害を受けた場合、個人情報が特定されたり実害がでたりする可能性も否定できません。
また、企業の場合には悪評の書き込みが広がることによって売上が低下するおそれもあります。
このような被害を回避するためにも、誹謗中傷記事は「一刻も早く消してほしい」と思うものですよね。
そこで今回は、ネット誹謗中傷記事・書き込みを削除する3つの方法をご紹介します。
ネット誹謗中傷記事・投稿を削除するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。
この3つの方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。
ここからは、3つの方法について詳しく見ていきましょう。
1つ目は、自分自身で書き込みの削除請求を行う方法です。
この方法には、「削除フォームによる削除」と「送信防止措置請求による削除」の2種類があります。
権利侵害の投稿が行われるサイト・掲示板には、「問い合わせフォーム」「削除申請フォーム」のように運営側に通報できるような機能が用意されていることが多くあります。
この削除申請フォームに必要事項を記入して送信すると、サイト管理者や運営会社が該当する記事を削除してくれることがあります。
ただ、何でも削除してもらえるというわけではありません。
基本的にはサイトに規定されているガイドラインや利用規約に違反したものが削除対象となるため、削除申請をする前には一度確認するようにしましょう。
この方法のメリットは、誰でも手軽に行うことができて費用もかからないことです。
場合によっては、削除依頼をしてから数日で対処してもらえる可能性もあります。
デメリットとしてあげられるのは、必ずしも書き込みが削除されるわけではないということです。
自分としては権利侵害にあてはまる投稿だと思っても、運営側が「違反しない」と判断すれば削除は行われません。
また、管理体制が甘いサイトだと申請自体が見過ごされてしまうこともあります。
プロバイダ責任制限法という法律に基づいて、送信防止措置依頼書を送付する方法です。
送信防止措置依頼書とは、権利侵害をする内容の記事や投稿を削除するようプロバイダやサイトの運営者に要求するための申請書です。
基本的には、必要事項を記入した紙を郵送することで申請できます。
送信防止措置依頼書には、以下のような内容を記載します。
書き方がわからない人は、「プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト」の書式を参考にするといいでしょう。(※)
下記の記事も併せて参考にしてみてください。
※サイトに送信防止措置請求に関する指示やテンプレートが用意されている場合には、それに従ってください。
この方法も、比較的費用がかかりません。
また、サイト側のガイドラインや禁止事項などに該当しない場合や、そもそもガイドラインなどが制定されていない場合にも、法的な権利の侵害(名誉毀損やプライバシーの侵害など)があれば削除を求めることが可能です。
この方法のデメリットは、強制力がないことです。
送信防止措置請求はあくまでも任意削除を要求するものですので、運営側が無視したり権利侵害がないと判断したりした場合には削除されません。
書類を送付したからといって絶対に削除されるわけではないことに注意しましょう。
2つ目に、弁護士に依頼する方法です。
自分で書き込み削除の手続きをするには、やはり限界があります。
自分で行う削除方法では削除に応じてもらえなかった場合や、どうすればわからない場合には弁護士に相談しましょう。
弁護士が対応する方法にも「任意交渉による削除」と「法的な対処による削除」の2種類があります。
順番にみていきましょう。
弁護士によって、任意削除を交渉する方法です。
つまり、方法①(自分でできる方法)の「削除フォームによる削除」と「送信防止措置請求による削除」を弁護士が代行します。
具体的な流れは、先述したものと同様です。
メリットとしては、弁護士から削除依頼がされることで本気度が伝わり、サイトの管理者や運営会社に真剣に応じてもらいやすくなることです。
また、弁護士が全て行ってくれることから、自分の手間が省けたり専門的な知識を活かしてより説得力のある請求をしてくれたりする利点もあります。
一方、任意交渉であるため強制力がないというデメリットがあります。
そのため、弁護士を通じたとしても、運営の判断によっては削除されない可能性もあります。
加えて、弁護士に依頼するための費用が発生します。
こちらは、法的手段によって削除を行う方法です。
具体的には、裁判所に削除の仮処分命令を出してもらいます。
仮処分は暫定的な判断によって認められるため、通常の裁判よりも短期間かつ低コストで行うことができます。
ちなみに、法的手段の1つとして「発信者情報開示請求」もあります。
この制度を利用することで、記事や投稿を作成した匿名相手を特定することが可能です。
損害賠償請求などをしたいという場合には、弁護士に発信者情報開示請求を依頼するのも良いでしょう。
こちらは任意削除とは違い、法的拘束力(強制力)があります。
そのため、仮処分命令が出た場合には確実に削除してもらうことができます。
デメリットは、費用・手間・時間がかかることです。
まず、数十万円単位の弁護士費用が発生します。
また、仮処分が認められるまでには数週間かかるケースが多いです。
さらに、認められると確実に削除できる一方で、認められないと削除命令は出してもらえません。
そのため、誹謗中傷されているページをプリントアウトしたり写真やスクリーンショットを撮ったりと、しっかり証拠保全する必要があります。
三つ目に、専門業者(誹謗中傷対策業者)に依頼する方法があります。
最初に注意してほしいのが、専門業者は記事・投稿自体の削除を行うわけではないということです。
この方法では、業者に検索結果の内容を一時的に変えてもらうことで、相対的に誹謗中傷の被害を減らしていきます。
それでは、専門業者はどのようにして誹謗中傷対策を行うのでしょうか。
業者が行うのは、「逆SEO対策」です。
例えば、Googleのサジェストや関連キーワードでマイナスイメージを喚起させるワードを表示しないようにしたり、良質なサイトを上位表示させてネガティブなサイトの表示順位を落として検索者の目に触れないようにしたりします。
完全にサイトの記事や投稿を消すことはできませんが、検索流入や閲覧数が減れば風評被害も小さくなるだろうという考え方です。
この方法のメリットは、サイトの運営側が削除に応じなくてもできることです。
裁判をする必要もないので、公の場でトラブルを明らかにする必要もありません。
成果報酬型でサービスを提供している業者もありますので、そのような業者に頼めば結果が伴わないのに高額な費用を払うといった心配もありません。
一番のデメリットは、問題の記事自体は残ってしまうので根本的な解決にはならないことです。
いくら検索流入が減るといっても記事が見られてしまう可能性はなくなりませんし、直接リンクを貼られてしまえばそこから閲覧することができてしまいます。
また、業者によってはグレーな方法で逆SEO対策を行っているところもあり、適切な業者を選ぶことが難しい点もデメリットと言えるでしょう。
専門業者の中には、依頼者の代わりに削除を行うことを請け負っているものが稀にありますが、このような業者に依頼してはいけません。
というのも、弁護士ではないのに削除代行を引き受ける行為は「非弁行為」という違法行為にあたるからです。(弁護士法72条)
逆SEO対策などではなく、「代わりに削除を行います!」といった旨の宣伝を行っている業者は使わないようにしましょう。
以上、誹謗中傷の記事や書き込みの削除方法について解説してきました。
上記で述べているように、記事の削除にはいろいろな手法があります。
まずは自分で削除フォームなどを使って削除請求してみて、無理なら弁護士に依頼して仮処分をしてもらう、というのが王道です。
何から始めて良いかわからない場合や、自分の手に余ると感じる場合には、ネット問題に強い弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。