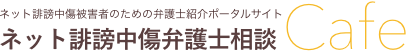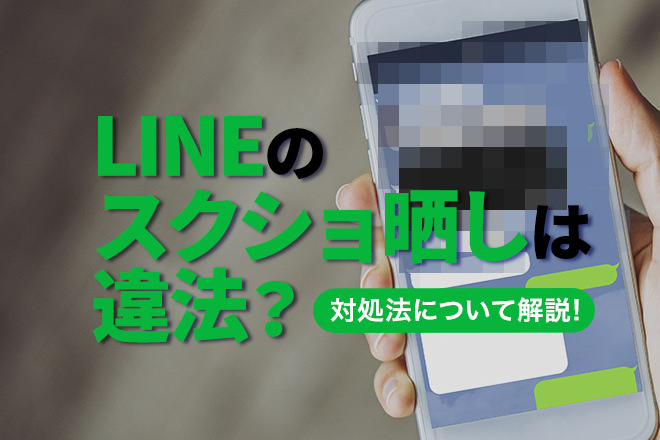肖像権侵害とは?事例とよくある質問から理解する肖像権の基本

近年では、TwitterやInstagramなど、ネットやSNS上で写真をあげる人も多いのではないでしょうか。
しかし、写真をネットにあげる際に気を付けたいのが「肖像権」です。
- 自分の写った写真を勝手に公開されたらどうすればいいの?
- 写真に一部でも他人が写っていたら肖像権侵害なの?
- 肖像権侵害になるとどうなるの?
今回は、上記のような悩みを抱える方に向けて肖像権について解説していきます。
肖像権とは?
肖像権の定義
そもそも「肖像権」とはどういった権利なのでしょうか。
肖像権とは、「何びとも、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由」のことをいうとされています(最高裁昭和44年12月24日判決)。
上記の定義は警察などの公権力に対する国民の自由としての定義でしたが、その後、私人同士の関係でも同様に認められています。
「人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されない(中略)法律上保護されるべき人格的利益を有し」、その「撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有する」
この判例では、「公表されない」ことについても言及されました。
現在「肖像権」と言う場合の内容は、「撮影されない」「公表されない」の両方のことを指していると言えるでしょう。
この判例から分かるように、肖像権は明文で保障されているわけではありません。
憲法13条の幸福追求権に基づいて、判例と解釈で認められているものです。
また、肖像権には、①人格権としてのプライバシー権と、②財産権としてのパブリシティ権という2つの側面があるとされています。
①人格権|プライバシー権
プライバシー権とは、「みだりに私生活を公開されない権利」や「自己に関する情報をコントロールする権利」のことをいいます。
誰しも、自分の私生活で勝手に写真を撮られたり、その写真をネットに無断で公開されたくありませんよね。
単に容姿であっても、私生活の一部であり、自己に関する情報ですので、自分の容姿を無断撮影されたり、写真を勝手に公表されたりしないよう主張できる権利をプライバシー権というのです。
②財産権|パブリシティ権
例えば、人気俳優の写真集を買ったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
写真集のように、タレントやアーティストといった著名人の写真(肖像)には商品としての高い財産的価値、「顧客吸引力」があります。
この財産的な価値を保護するのが「パブリシティ権」です(最高裁平成24年2月2日判決)。
厳密には肖像権とは異なりますが、しばしば肖像権の一側面として問題になります。
そのため、例えば誰かが有名人を隠し撮りして、その写真を売って儲けると人格権としての肖像権侵害であると同時に、「パブリシティ権」の侵害にもなります。
肖像権侵害になるとどうなるの?
刑事責任
たとえ撮影行為や写真の投稿行為が、肖像権侵害になったとしても、そのこと自体に刑法上の刑事罰があるわけではありません。
とはいえ、盗撮行為は迷惑防止条例違反として処罰される可能性があります。
民事責任
肖像権侵害は、民法709条の「不法行為」にあたります。
肖像権侵害を受けた人は、それによる精神的苦痛について、不法行為に基づく損害賠償を請求できます。
また、写真が公開されたことで引っ越しをしなければならなくなったなど、実害を被った場合にはその分の損害賠償を相当な範囲で請求することもできます。
なお、パブリシティ権侵害にもなる場合は、この精神的苦痛のほか、商業的・財産的価値の侵害についても損害賠償請求が可能です。
また、ネット上に公開された写真や動画の削除請求も可能ですし、ケースによっては掲載前の差し止め請求も可能です(東京地裁平成21年8月13日決定・判例タイムズ1309号282頁)。
どこからが肖像権侵害?判例と基準とは
先述したように、肖像権は明文で規定されているわけではないので、曖昧なところも多々あります。
その中で、どこからが肖像権侵害といえるのかについては、冒頭でご紹介した最高裁平成17年11月10日判決が参考になります。
この判例は、週刊誌が和歌山毒物カレー事件の被告の写真を隠し撮りしたことに対して訴えられた事例です。
判決の中で、最高裁は肖像権侵害にあたるか否かを判断する方法について「受忍限度論」を採用しました。
「受忍限度論」とは、侵害された権利・法的利益の内容や被害の程度、侵害行為の態様・動機・目的など、諸事情を考慮したうえで、侵害が「社会生活上受忍するべき限度」を超えた場合に、違法な侵害として損害賠償責任が生じるという考え方です。平たく言えば、「諸般の事情から裁判所の裁量で判断する」ということです。
本件では、その考慮するべき諸事情の例として、次のものが指摘されています。
- ①被撮影者(撮られた人)の社会的地位
- ②撮影された被撮影者の活動内容
- ③撮影の場所
- ④撮影の目的
- ⑤撮影の態様
- ⑥撮影の必要性
そのうえで、勾留理由開示手続の法廷で、写真週刊誌のカメラマンが、手錠と腰縄をつけられた被疑者の姿を隠し撮りしたという本件事案では、
- 被撮影者が撮影されることを予想できる場所ではないこと(③)
- 隠し撮りであったこと(⑤)
- 手錠や腰縄をつけられている姿をわざわざ撮影して公表する必要性がなかったこと(⑥)
などから、受忍の限度を超えると評価し、肖像権侵害が認められました。
顔が写っていない写真は?後ろ姿は?肖像権侵害の具体例
肖像権侵害の有無は、この受忍限度論のように、諸事情を考慮した総合判断ですから、最終的には裁判官の匙加減で決まります。
ただ、諸事情の中でも、判断の分かれ目となるポイントはありますから、これを以下にご説明します。
肖像権侵害の有無を判断するポイント
肖像権侵害かどうかを考えるときには主に以下の点を確認するようにしましょう。
- ①撮影された人が特定できる画像かどうか
- ②風景写真などに偶然写り込んだのではなく、撮影された本人がメインとなって撮影されている画像かどうか
- ③画像を公表したかどうか
- ④本人の許諾を得たかどうか
- ⑤撮影場所は公開されている場所かどうか
- ⑥撮影方法は隠し撮りかどうか
- ⑦水着や下着姿など、一般的に公開を望まない姿かどうか
- ⑧撮影の目的、公表の目的はなにか
①~④について、少し詳しくご説明します。
①撮影された人が特定できる画像かどうか
顔がはっきりと写っている写真のように、本人が写真から特定できてしまう場合には肖像権侵害になる可能性が高くなります。
集合写真も、一人一人の顔がはっきり映っていれば同じです。
逆に、顔がボカシやモザイクで隠されていたり、腕や足などの体の一部が写っているだけで、個人を特定できないものは、通常は肖像権侵害とはなりません。
②風景写真などに偶然写ったのではなく、撮影された本人がメインとして撮影された画像かどうか
例えば、お祭り・イベント・交差点など、多くの人の目に触れる公開された場所でたまたま歩いている姿が写り込んでしまったとき(お祭りの様子を撮ろうとして多くの客のうちの一人として写ってしまった場合など)には、その姿はいわば風景の一部として撮影されているに過ぎないので、受忍限度を超えて肖像権侵害となるケースは少ないでしょう。
一方、「その人自身」をメインで撮ったのだとわかる写真は、肖像権侵害になる可能性が高まります。
③画像を公表したかどうか
インターネット上のブログ・TwitterといったSNSなど、不特定多数の人に見られるようなサイトに投稿するなど、画像を公表した場合は肖像権侵害となる可能性が高くなります。
④本人の許諾を得たかどうか
これは当たり前のことですが、撮影された本人が「ネットにあげていいですよ」と許可してくれたのであれば、肖像権侵害になりません。
ここで注意したいのは、”撮影許可”と”撮影した写真を公開する許可”は別であるということです。
「撮影していいよ」と言われても、「撮影した写真をネットにあげていいよ」という許可をもらっていない場合には肖像権侵害になってしまうので、気を付けましょう。
上記にあてはまっている場合には、写真をネットに投稿しない・写真を加工するといった配慮が必要です。
肖像権侵害でも違法ではないケースとは?
ここまで、肖像権侵害の考え方をご説明してきましたが、実際に肖像権侵害だと評価される場合であっても、損害賠償請求は認められないこともあります。
不法行為の成立には「違法性」が必要ですから、侵害行為が違法ではない場合には、損害賠償は認められません。
例えば、民主政を機能させる「表現の自由」の観点からは、たとえ肖像権侵害があっても免責されるべき場合を認める必要があります。
ある裁判例では、違法ではないとされる基準として以下の3つを挙げています(東京地裁平成17年9月27日判決・判例時報1917号101頁)。
- ①公共の利害に関する事項と密接な関係があること
- ②もっぱら公益を図る目的であること
- ③撮影方法・発表方法が、②の目的に照らし相当なものであること
肖像権侵害に関するよくある質問
-
顔にモザイクをかければ肖像権侵害にならない?肖像権侵害になるかどうかは、相手を特定できるかどうかと密接に関わります。
顔にモザイクやマークをあてても、モザイクが薄かったりマークが小さかったりして本人が特定できてしまう場合には、肖像権侵害になることがあります。
また、顔がわからないとしても、体や服装などの写っている部分から本人が推測できてしまう場合にも、肖像権侵害となる可能性は否定できません。 -
後ろ姿の写真なら大丈夫?後ろ姿であっても、「本人特定の可能性」によって判断します。
ごく一般的な後ろ姿で対象者が誰か判別できない場合には、基本的に肖像権侵害となりません。
しかし、身体的な特徴や歩き方などから後ろ姿でも本人を推測できるのであれば、肖像権侵害になる可能性もあります。
もちろん、「〇〇の後ろ姿~」という文章をつけて投稿したときには本人が特定できてしまうため、より肖像権侵害となる可能性は高くなります。 -
警察などの公務員を撮影するのは肖像権侵害にならない?公務員も人間ですから当然に肖像権があります。警察官でも、消防士でも、市役所の事務職でも全く同じです。
肖像権侵害の有無は、諸事情を考慮したうえで、受忍限度内か否かを判断して決められます。公務員だからといって、撮影されること、画像を公表されることを受忍しなくてはならないとする理由は全くありません。
例えば、警察や消防士が、家族で旅行をしているときのように私的な場面で勝手に撮影すること、その写真を公表することは肖像権侵害になる可能性が高いでしょう。
一方、火災事現場で消防士が消火活動している姿や、警察官が路上で職務質問を行っている姿を撮影すること、画像を公表することは、公開された場所で、公務に携わっている姿ですから、承諾を得ていなくとも、通常は、受忍限度を超えることはないと判断されるでしょう。
もちろん、これが報道目的の場合はより一層、受忍限度を超えないと判断される可能性が高くなりますし、仮に限度を超えたとしても、「公共の利害に関する事項」として違法とされないでしょう。
これに対し、例えば警察官の公務中の姿を順次撮影し、その画像を「××県○○署警察官の連中」と題してネットに公表した場合はどうでしょうか?
公務員といえども、その一人一人の顔写真を世界に公開する必要性は疑問ですし、このようなことが行われれば、現実問題として各警察官の生命身体を危険にさらしかねず、警察の業務にも著しい支障を生じさせる可能性があることは明らかですから、受忍限度を超えると判断されるでしょう。 -
芸能人・スポーツ選手といった著名人の肖像権は?「有名人を撮影しても肖像権侵害にならない」と思われていることもありますが、それは間違いです。
著名人にも肖像権があります。
ただし、一般人よりは受忍するべき限度が広いと判断されるでしょう。
写真撮影が許されている場所(イベント会場、競技会場など)での撮影はもちろん適法ですし、投稿しても通常は違法になりません。
また冒頭に説明したように、有名人の写真や動画には「パブリシティ権」が認められます。
勝手に撮影・販売して利益を得たり、それによって本来権利者が得られたはずの利益が減ったりすると、「パブリシティ権侵害」として高額な賠償金を請求される可能性があるので注意しましょう。 -
似顔絵やイラストが肖像権侵害になるって本当?似顔絵やイラストの場合にも、肖像権侵害となる可能性があるので要注意です。
前記の最高裁判例でも、「人は、自己事故の容ぼうなどを描写したイラスト画についても、これをみだりに好評されない人格的利益を有する」と判断されており、イラストによる肖像権侵害の可能性が認められています。 -
防犯カメラって肖像権侵害にならないの?防犯カメラの撮影が肖像権侵害となるか否かも、個別の事情から、受忍限度を超えているかどうかによって判断されます。
例えば、コンビニの店主が、店内に防犯カメラを設置して客を撮影し、その画像をビデオテープに録画保存していた行為が、客の肖像権を侵害したとして慰謝料を請求された事件の裁判例があります。
この裁判例では受忍限度を超えない(肖像権侵害が認められない)とされました(名古屋地裁平成16年7月16日判決)。
判断のポイントは次のとおりです。
①撮影と録画保存は万引や強盗に対処するためで、コンビニ強盗が多発し、地域の防犯協議会やコンビニ本部からも、防犯カメラの設置が推奨されいた(録画の目的が正当)
②隠し撮りではなく客からもカメラの設置が明らかで、しかも撮影していることを知らせる掲示もある
③固定されたカメラで、特定の客を追跡撮影するようなものではない
④録画テープも1週間で消去していた -
故人の肖像権は?死後は勝手に写真を使ってもいいの?故人に肖像権はありません。
死者は私権の享有主体ではないので、肖像権の構成要素である人格権も財産権もありません。財産権については、死者が生前に有していた権利は相続人に承継されますが、人格権は相続の対象外です。
ただし、生前に肖像権が侵害され、すでにこれを原因とする損害賠償請求権という具体的な請求権が発生していたと評価できる場合には、その請求権を相続人が承継することになります。
また、死後に故人の写真を勝手に使うことは、遺族に対する不法行為となる場合があると理解しておけば足りるでしょう。
亡くなった親族の写真を無断で使用されることが、遺族にとって受忍限度を超えているか否かも、個別事情による判断となります。
ただし、有名人のパブリシティー権が、有名人本人の死後も認められるかは問題があります。
例えば、ある女優が死亡した後に、そのブロマイドを勝手に販売して収益をあげる行為が無制約に許されるとは到底思えないからです。
しかし、この「パブリシティー権の相続性」については、議論がされている段階で定説はなく、裁判例もありません。