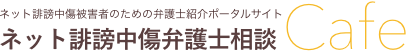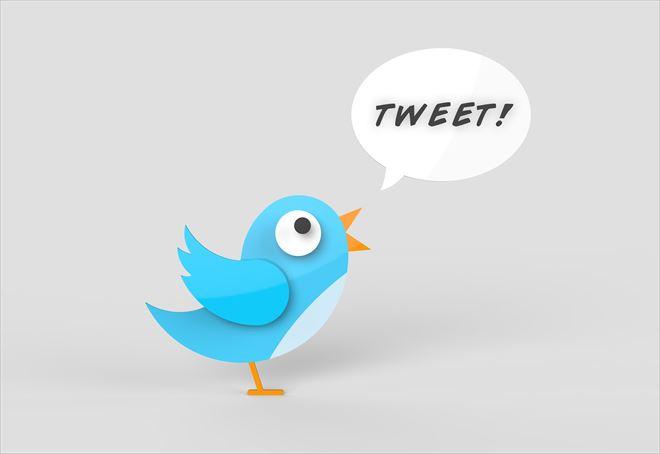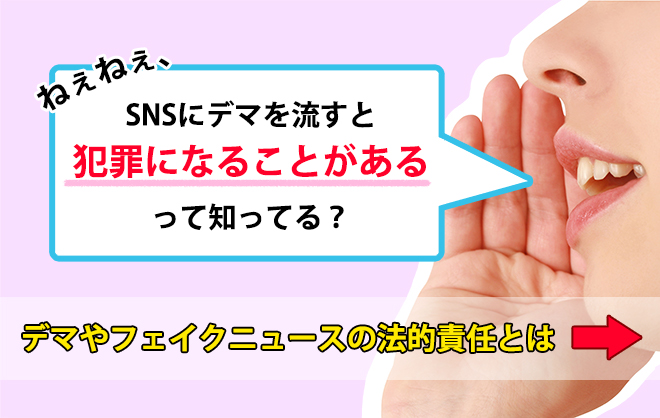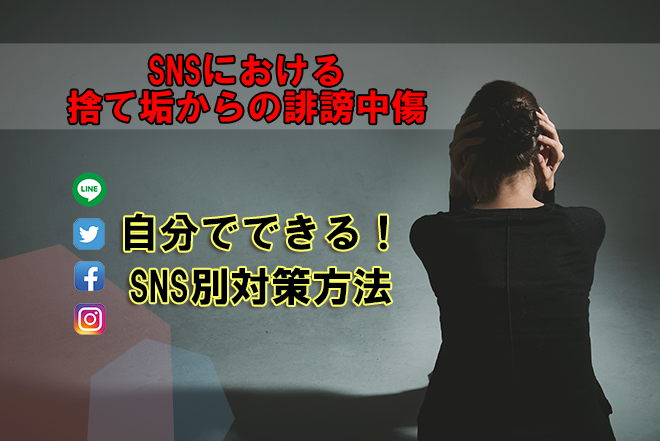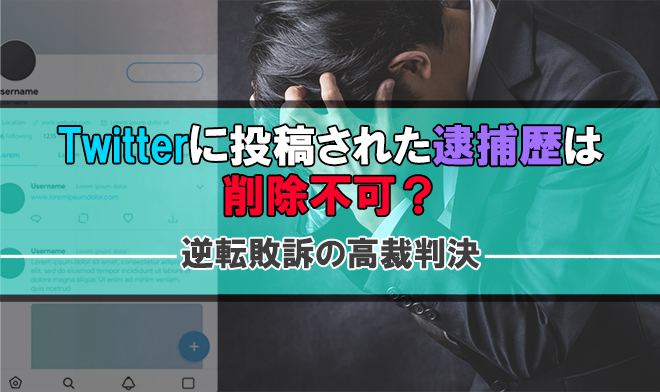企業でSNSを運用する注意点|SNS活用事例と炎上トラブルを解説

今では誰しも利用することが当たり前になっている「SNS」。
近年は、このSNSを活用してマーケティングを行う企業も多くなっています。
ただ、導入したいと考えている人の中には、
「SNSで炎上したらどうしよう」
「どうやれば上手く活用できるの?」
と考えている社員の方も多いでしょう。
そこで今回は、企業がSNSアカウントを運用する際のポイントなどをご紹介していきたいと思います!
企業がSNSを活用するメリット
アライドアーキテクツ株式会社の調査結果によると、Twitterで企業の公式アカウントをフォローしている人は50%を超え、SNSが商品を購入するきっかけとなった人は77%ほどにのぼるといわれています。
【参考】2019年度「Twitter企業公式アカウント」の利用実態を調査
また、多くの企業でSNSを導入する傾向にあり、Twitter・Instagram・Facebook・LINE・YouTubeなど、特徴に応じて色んな種類のSNSを複数活用しているところも多いようです。
SNSから直接収益を得ることは難しいかもしれませんが、知名度の向上や集客など、上手く使えば間接的に利益をもたらすことができるでしょう。
SNS運用の活用事例
では、SNSを利用した活用事例とはどのようなものがあるのでしょうか。
今回は、特にTwitterでの方法に注目してみましょう。
タグ付けによる拡散
「感想は#××で呟いてね」
上記のように、会社で専用のタグを作り、顧客に感想や意見を呟いてもらう方法があります。
タグで簡単に検索できるため、感想のサーチがしやすくなると同時に、感想ツイートを見た人が気になって調べてくれるといった拡散効果もあります。
下記はANAのツイートですが、小規模な企業でも他の広報手段と合わせて効果的に使うことができます。
【ANA飛行機写真】
出発準備OK✈️
(Photo:@JREASTe353kei)新しい空旅へ✨
⇒https://t.co/MUFFFUpFx2ANAの飛行機は「#ソラマニ_ヒコーキ」をつけて投稿してね🌟ANAの各メディアでご紹介していきます❣ pic.twitter.com/xMeQedgkJS
— ANA旅のつぶやき【公式】 (@ANA_travel_info) November 4, 2020
キャンペーンによるフォロワー獲得
このように、プレゼントを用意してフォロワーを増やしたり、リツイートで拡散を狙う会社もあります。
この方法はツイートを見たユーザーから他のユーザーへと広まりやすく、会社にとってもユーザーにとってもお得であるといえます。
次のツイートのように、中~大規模な企業で行われることが多いです。
\本日最終日🎉/#ファミマの炭火焼きとり がその場で当たる👀
炭火焼きとり もも(塩)or もも(タレ)の無料引換券を10万名様にプレゼント🤗
▼応募方法
①@famima_nowをフォロー
②この投稿をRT🔄
③特設サイトから抽選に参加
※沖縄県は対象外
11/5までがチャンス!
🔽特設サイトはこちらから🔽— ファミリーマート (@famima_now) November 5, 2020
視覚に訴える魅力的な宣伝
動画や画像を利用して、より視覚的に商品の魅力を伝えます。
特に、美味しそうなグルメがご飯時に流れてくると、ついつい食べたくなってしまうものです。
外食企業や食品メーカー、レシピサイトなどで行われることが多いですが、動画や画像は訴求力があるため、様々な使い方ができます。
期間限定11/15まで
「果実いっぱいフルーツボンブ」キウイ🥝、苺🍓、黄桃🍑、バナナ🍌
フルーツをふんだんに使ったケーキです🎵
byりこ#シャトレーゼ #ケーキ pic.twitter.com/ZPHZdXaSxb— シャトレーゼ【公式】 (@chateraise_jp) November 3, 2020
ユニークな”中の人”
単純に機械的な公式アカウントとして運営するのではなく、投稿する人(中の人)の個性を活かしたツイートをする方法もあります。
ときには他の企業アカウントの人とリプライを送りあったり、コントのような投稿を行うことで話題性をつけることもできます。
「あつ森」に『タニタ島』があったら、これでもかと健康診断もするし、健康的なタニタ食堂も提供させていただきます。任天堂さん何卒よろしくお願いします。
— 株式会社タニタ (@TANITAofficial) November 2, 2020
企業SNSでのトラブル事例
成功事例もある一方、不適切な投稿をしてしまうと瞬く間に炎上してしまうのがSNSのデメリットです。
どのようなトラブルがあったのか、過去の事例を見てみましょう。
企業SNSのトラブルは非常に数多く発生しており、枚挙に暇がないため、ここでは一部のみをご紹介します。
不適切な内容や宣伝の投稿
8月9日に、あるテーマパークの公式アカウントが「なんでもない日、おめでとう」という投稿をTwitterにしました。
ただ、8月9日は長崎に原爆が落とされた日であり、それを「なんでもない日」と表現するのは不謹慎だと非難が相次ぎました。
また、日用品メーカーがタンポンのCMを投稿した際、その内容が男性のためにタンポンを選ぶといった意図が見受けられるようなものであったため、女性から批判されたケースもあります。
タイツの日のPR
タイツメーカーのアツギは、11月2日のタイツの日にあわせて「#ラブタイツ」というハッシュタグをつけて、タイツを履いた女性のイラストなどを投稿するプロモーション企画を行いました。
しかし、これが「女性を性的搾取の対象としている」などと批判され、一時は炎上状態となりました。
アツギは11月3日にはツイートを削除・運用停止し、公式サイトでも謝罪文を掲載しています。
【参考PDF】アツギ:ラブタイツキャンペーンに関するお詫びとご報告
情報の漏洩
従業員が「□□(芸能人)が来た」という投稿をしてしまったり、自身が投稿しなくとも家族や友人に話したことで情報が漏洩し、炎上することがあります。
また、大手通信会社の役員がプロジェクトのリリースを公式発表の前にSNSで公表してしまい、コンプライアンス問題が起きた事例もあります。
役員クラスがこうした漏洩をしてしまうと、企業の体制自体に不信感が生じることもあり、非常に注意が必要です。
会社の悪い評判の流出
ある印刷会社の公式アカウントで「お前のやっていることはムダと言われたのでアカウントを消します」という投稿がされました。
このように、会社にネガティブな投稿をされることで、会社のイメージダウンに繋がったり信頼が低下したりする恐れがあります。
企業でSNSを使うときの注意点
以上のように、SNSを使うとトラブルが起きる可能性もあります。
ここからは、炎上しないために注意する点をご紹介していきます。
SNS運用の注意点① ガイドラインや運用ポリシーを決めておく
どんなコンセプトで、どんな内容の投稿を行うのか決めておきましょう。
投稿内容の自由度を高めるのであれば、運営する人にネットリテラシーやコンプライアンス教育を行い、適切な投稿を心がけてもらう必要があります。
また、万が一トラブルが起きたときにどうするのか、マニュアルを作成するのも忘れないでください。
SNS運用の注意点② 世界中の人が見ていることを意識する
SNSは日本に限らず、世界中の色んな人が見ることができます。
そのため、ターゲット層や見解のズレが生じ、一部では好評だった商品や宣伝がSNSにあげた途端炎上するという可能性も十分にあり得ます。
人種差別的な内容になっていないか、男女の性別が絡むような宣伝でイメージの押し付けになっていないか、色んな視点から注意することが必要です。
SNS運用の注意点③ SNS内容を確認する
運営者である本人が意識していなくとも、炎上に繋がるような投稿をしてしまうこともあるでしょう。
そこで、一人に運用を任せるのではなく、投稿内容を確認する部署や部門を設けるようにしましょう。
人手が足りない場合でも、運用と確認と最低2人でダブルチェックを行うことがおすすめです。
モラルに欠けていないか、企業のイメージに沿った投稿をしているか、SNS上の反応はどうか、第三者目線で確認することが大切です。
SNS運用の注意点④ 従業員にも教育を行う
先述したように、従業員やその家族のSNSから炎上が起きるケースもあります。
個人アカウントでSNSを使うときの利用方法やコンプライアンスについての教育はしっかりしておきましょう。
SNS運用の注意点⑤ ネット炎上保険に加入しておく
最近では、ネットで炎上した際に使える保険を販売している会社もあります。
また、SNSを監視して炎上を察知してくれるサービスもあるので、金銭的に余裕があるのであれば導入してもいいかもしれません。
炎上トラブルを起こしてしまったときの対処法
もし炎上してしまった場合は、その後の対応が重要です。
トラブル後の対処① 問題のある投稿を保存
原因となった投稿を消す前に、スクリーンショットやプリントアウトで保存しておくようにしましょう。
何か起きた時の証拠や、どこが問題になったのか見直しをする際に役立てることができます。
トラブル後の対処② 丁寧な謝罪を行う
ただ単純に投稿を消して無かったことにしてしまうと、さらに批判を集めることになります。
丁寧な謝罪文をSNSと自社サイト上に投稿し、真摯に対応して投稿を削除するようにしましょう。
事例でご紹介したアツギの「#ラブタイツ」プロモーションについては、迅速かつ丁寧にこの対応がされたと言えるでしょう。
トラブル後の対処③ 原因の究明・事実確認を行う
投稿の内容によっては、原因の究明と事実確認が大切になります。
特に、会社の不祥事などが発覚した場合、顧客への説明と当事者への対処が急がれます。
トラブル後の対処④ 場合によっては法的措置を行う
事実無根な投稿など、嫌がらせ目的でSNS被害にあった場合は、該当する投稿を削除してもらうことで虚偽の事実が拡散しないように防ぐ必要があります。
また、悪質さによっては投稿者を特定し、処罰することも検討しましょう。
まとめ
以上が、企業がSNSを運用する際に気を付けるポイントでした。
先述したように、SNSは上手に使えば利益に、下手に使えば評判を落とすことに繋がります。
運用を検討しているのであれば、使い方や投稿内容を事前に確認し、炎上が起こらないように気を付けましょう。